傷病鳥獣の保護記録(まとめ)
監修:黒田 隆司 編者:水野哲男 青木久子 津野修一 和歌山県立日高高校生物部 1998年6月30日発行
和歌山県御坊市付近における傷病鳥獣の保護記録(1975年2月~1998年3月)
まとめ
津野 修一
この記録は1975年2月から1998年3月末までに和歌山県立日高高等学校生物部に持ち込まれた傷病鳥獣の保護記録(保護記録の個別表は、このホームページには掲載していません)を表とグラフにまとめたものである。
この傷病鳥獣の保護記録は、私が入部する約1年前から始まっていて、私自身もこの傷病鳥獣の保護活動を通して貴重な経験をさせて頂いた。私が入部した当時の様子は、部室内にはキジバト、外には猟銃で羽を撃たれたトビが飼われていた。その頃アナグマがよく保護されたので、部室周辺は傷病鳥獣の糞やエサでとても悪臭がひどかった。また、後輩たちは埋葬班をつくって、部室の裏手に亡くなった鳥獣を埋葬し供養していた。この活動は部員達にとって日頃の調査より地味で、とても根気のいるものであった。しかし、保護鳥獣への思いは深く、同時に生命の尊さを学んだものだ。
このデータを分析するにあたり、長年にわたり傷病鳥獣の保護活動をされた、日高高校生物部顧問の先生及び部員の皆様に敬意を表するとともに、元部員を代表してデータの分析に携われたことを光栄に思う。
用語の解説と表のみかた
- 年別・種別集計表の鳥類の渡り区分について
この渡り区分は、御坊市周辺の日高地方を基準に考えて、分類している。それに最近では漂鳥(日本国内を季節によって移動する「日本の北部から南部へ、または高地から低地へ移動する」鳥)という分類が使われないと聞き、ツミ、ハイタカ、アオバト、トラツグミ等の分類や、主に日本に夏鳥として渡来するが、御坊周辺では通過鳥であり龍神村付近では夏鳥という、コマドリ、オオルリ等の分類。それにアマサギのように一般的には夏鳥だが当地方では一年中見られ、特に渡りの時期に多く見られる鳥の分類に頭を悩ました。以下に、その渡りの区分を説明する。
留鳥:当地方で一年中見られる鳥
夏鳥:春に南の地方から渡ってきて繁殖し、秋には南の地方に渡る鳥
冬鳥:秋に北の地方から渡ってきて越冬し、春には北の地方に渡る鳥
旅鳥:主に春、秋の時期に、渡りの途中で当地方を通過するだけの鳥
迷鳥:当地方ではめったに見られず、なんらかの原因により渡りのコースからはずれ迷って来た鳥 - 保護記録の件数の扱いについて ひな等に関して、たとえば、3羽一度に保護された場合、基本的に1件として扱うのだが、1羽ずつ記録をつけている場合がある。この場合、あくまでも記録簿を尊重してまとめてあるので、すべての表とグラフは、記録簿通りの件数で作成してある。
以下がそれに該当する。No233・234のヒヨドリ、No243~245のホオジロ、No246~248のキジ、No249~251のフクロウ、No273~274のキジバト、No281~283・No288~289のハシボソガラス。 - 保護原因・保護後の経過について
保護:原因については、以下のとおり分類してある。
衰弱:外傷もなく、病気とも判断できない弱っているもの
傷害:交通事故、けが、猟銃による傷害、釣り糸による傷害、網・わなに捕まっていた等の原因によるもの
死体:死体で持ち込まれたもの(ひな・巣立ちびな等も死体であった場合はこれに含まれる)
ひな:巣を壊された等の理由により保護された巣立ちしていないひな
巣立ちびな:巣立ち後間もないひな
薬害:あきらかに農薬の害と思われるもの
病気:あきらかに病気と思われるもの
卵:卵で持ち込まれたもの
幼獣:生後間もない哺乳類
保護後の経過については、以下のとおり分類してある。
放鳥:元気になり放した鳥類
放獣:元気になり放した哺乳類
死亡:保護したときは生きていたが、その後死亡したもの
死体:死体で持ち込まれたもの(保護原因の数値と一致する)
飼い主に返却:飼い鳥若しくは、伝書鳩(ドバト)で飼い主が見つかったもの
飼育依頼:セキセイインコ等の飼い鳥で、部員等が自宅で飼育したもの
他校へ:御坊商工高等学校(現在は紀央館)等の他校に引き渡しをしたもの
部員長期飼育:羽の切断等で野生に戻れず、部員が自宅で長期に飼育したもの
孵化せず:卵で持ち込まれ、孵化しなかったもの
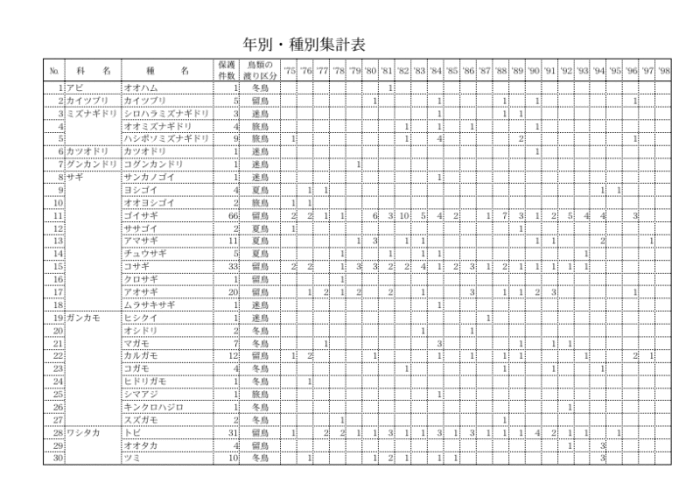
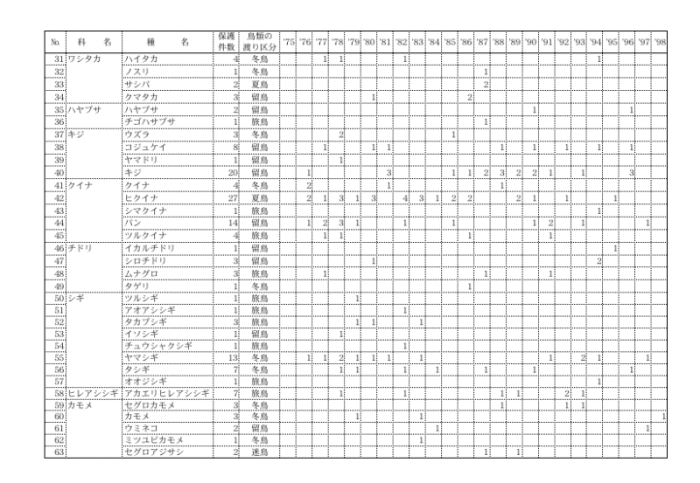
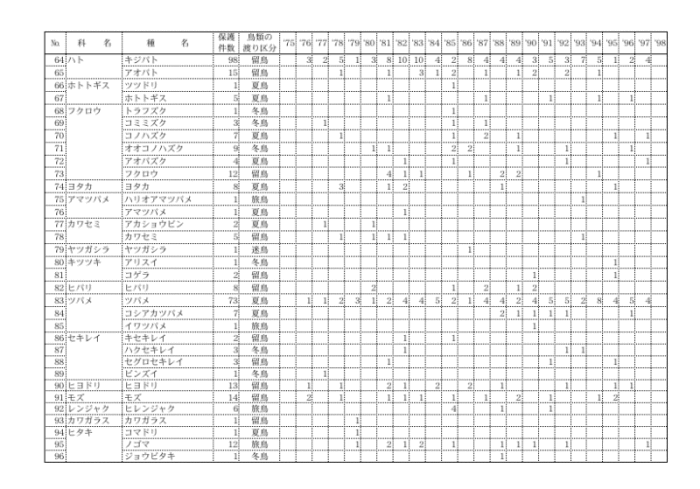
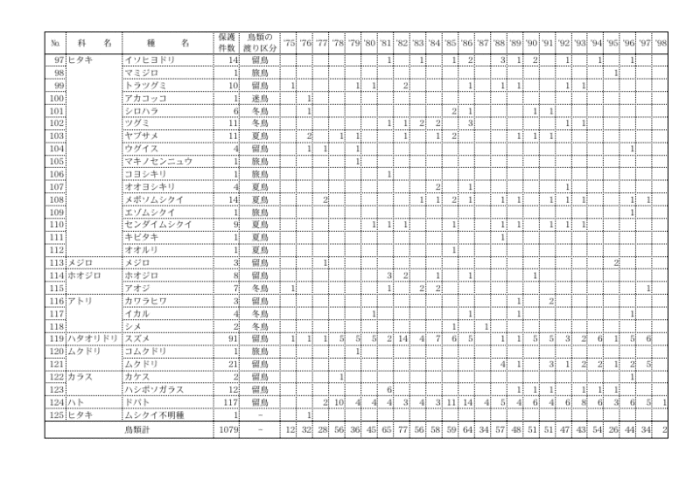
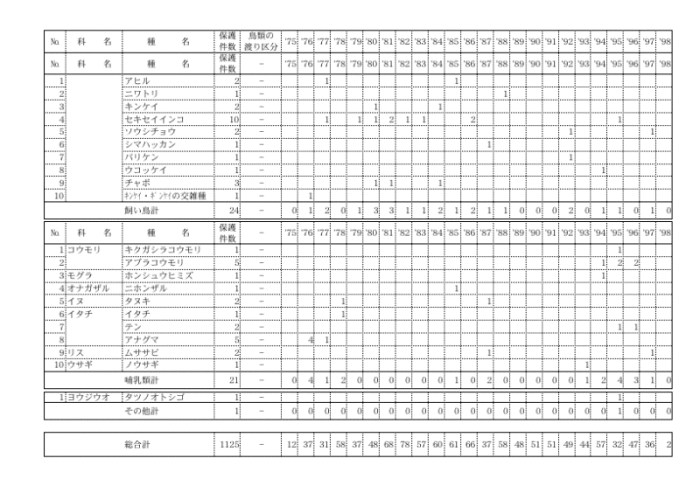
各図の集計結果及び考察
保護場所の市町村別割合と保護原因別割合
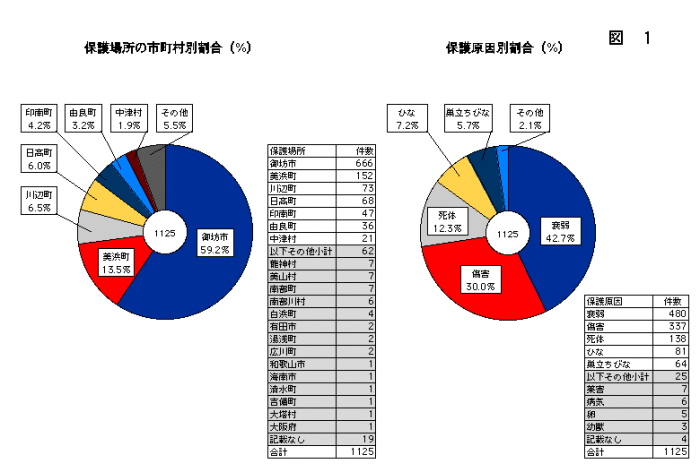
保護場所の市町村別割合は、日高高校のある御坊市が圧倒的に保護件数が多く、666件で59.2%、以下、美浜町152件で13.5%、川辺町73件で6.5%、日高町68件で6.0%、印南町47件で4.2%、由良町36件で3.2%、中津村21件で1.9%、その他62件で5.5%と図1左側のグラフに示す通りである。
また、保護原因別割合は、衰弱480件で42.7%、傷害337件で30.0%、死体138件で12.3%、ひな81件で7.2%、巣立ちびな64件で5.7%、その他25件で2.1%と図1右側のグラフに示す通りである。
保護後の経過割合と鳥類の渡り区分別割合
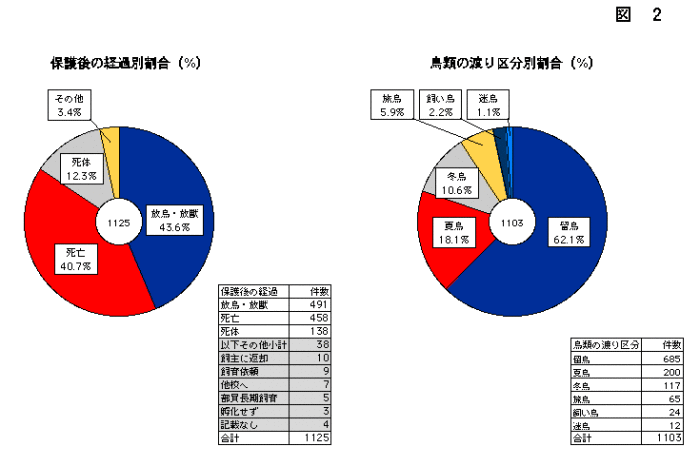
保護後の経過割合は、放鳥・放獣491件で43.6%、死亡458件で40.7%、死体138件で12.3%、その他38件で3.4%と図2左側のグラフに示す通りである。
また、鳥類の渡り区分別割合は、留鳥685件で62.1%、夏鳥200件で18.1%、冬鳥117件で10.6%、旅鳥65件で5.9%、飼い鳥24件で2.2%、迷鳥12件で1.1%と図2右側のグラフに示す通りである。(注意:ドバトに関しては留鳥に分類した。)
保護原因別の放鳥・放獣率,死亡率
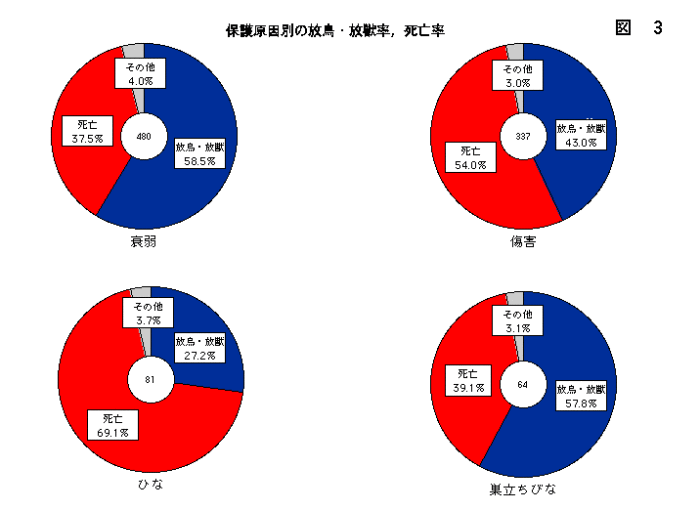
- 衰弱で保護された傷病鳥獣は、480件あり放鳥・放獣が58.5%、死亡が37.5%、その他が4.0%である。
- 傷害で保護された傷病鳥獣は、337件あり放鳥・放獣が43.0%、死亡が54.0%、その他が3.0%である。
- ひなで保護された傷病鳥獣は、81件あり放鳥・放獣が27.2%、死亡が69.1%、その他が3.7%である。
- 巣立ちびなで保護された傷病鳥獣は、64件あり放鳥・放獣が57.8%、死亡が39.1%、その他が3.1%である。
その結果、図3に示すように衰弱による放鳥・放獣率が一番高く58.5%、つづいて巣立ちびな57.8%・傷害43.0%で、ひなの放鳥・放獣率が極端に低く27.2%の順となった。
年別放鳥・放獣率,死亡率
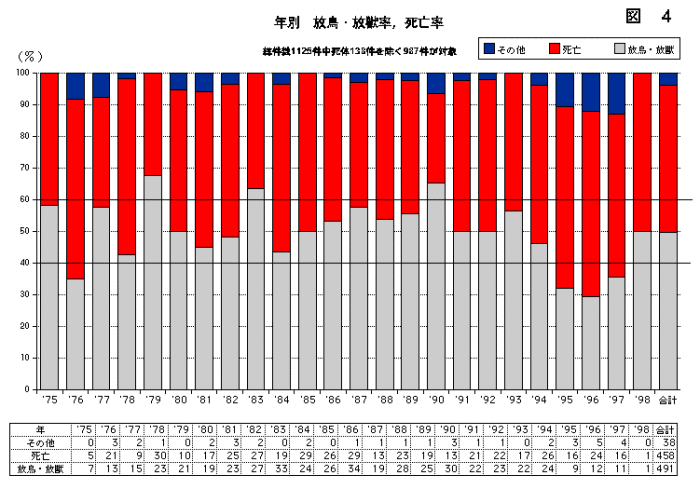
図4では総件数1125件中、死体で届けられた138件を除いた987件を対象に、年別に放鳥・放獣率,死亡率の推移を示してある。放鳥・放獣率が60%を超えた年が1979年の67.7%・1983年の63.5%・1990年の65.2%となり、40%を下回った年が1976年の35.1%、1995年の32.1%、1996年の29.3%、1997年の35.5%で、合計値の放鳥・放獣率は49.8%となった。
月別保護件数
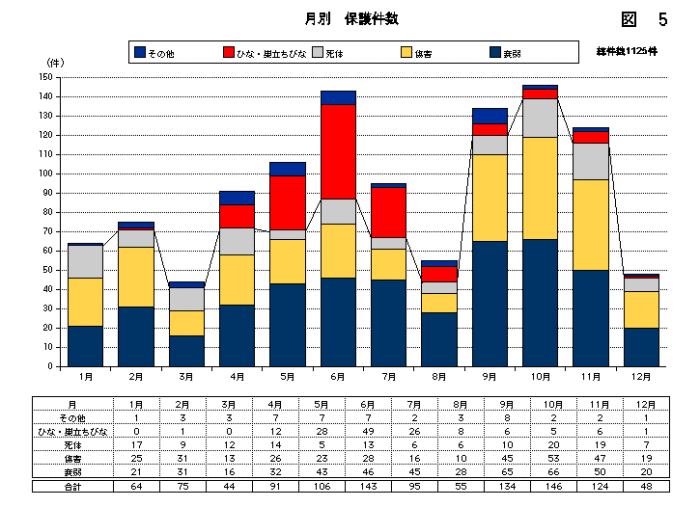
図5では、総件数を月別に衰弱・傷害・死体・ひな(巣立ちびな)・その他に分類し、月別に保護の件数を集計した。そして、衰弱・傷害・死体の合計値を線で結び、これらの原因によって保護された月別件数にどのような変化がみられるかをまとめた。衰弱・傷害・死体の合計値は9月・10月・11月と秋の渡りシーズンに多く、ひなの保護は繁殖期後半の6月に多かった。またひなの保護で9月・10月・11月の繁殖期でない時期の保護は、大半がドバト・キジバトであった。
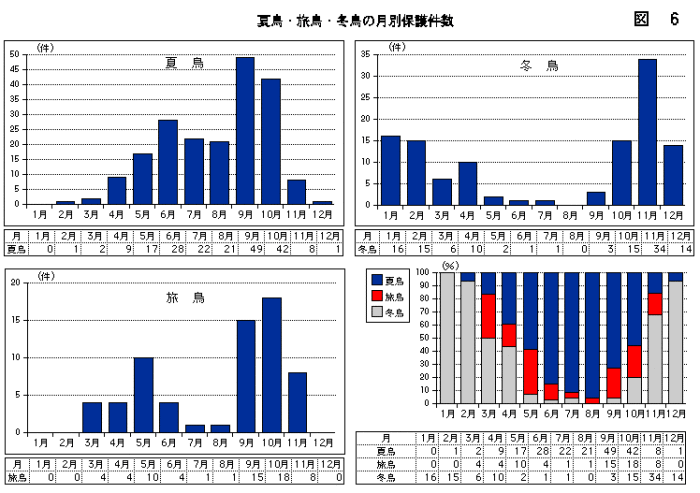
図6では、それぞれ夏鳥・旅鳥・冬鳥について月別保護件数を集計し、件数とその割合を図に示した。渡り区分別のピーク値は、夏鳥は9月、旅鳥が10月、冬鳥は11月であった。また、渡り区分からみれば時期はずれといえるものが、夏鳥では2月1件ササゴイ、3月2件コノハズク・アマサギ、12月1件ヨシゴイで、旅鳥では7月1件アオアシシギ、8月1件シマアジで、冬鳥では5月2件マガモ・シロハラ、6月1件ハクセキレイ、7月1件マガモであった。(参考に夏鳥の保護で6月・7月は、6月1件アマサギ・7月2件オオヨシキリ・アオバズクの保護を除いてはツバメとコシアカツバメばかりであった。)
年別保護件数
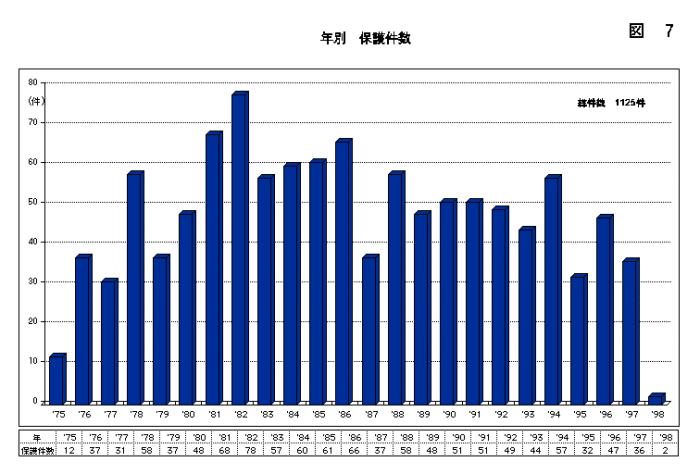
図7では、1975年から始まった傷病鳥獣の保護件数を年別にまとめた。1998年は3月末までの記録となっている。
1982年の78件をピークに毎年約50件の傷病鳥獣が生物部に持ち込まれたことになる。
まとめ
1975年から1998年3月末までの23年間・1125件の保護記録は、当地方の鳥の生息状況並びに渡り区分を考えるにあたり貴重な記録と言える。特に、日頃観察する事の少ないミズナギドリの保護に注目できたので、以下の表を参考に紹介する。
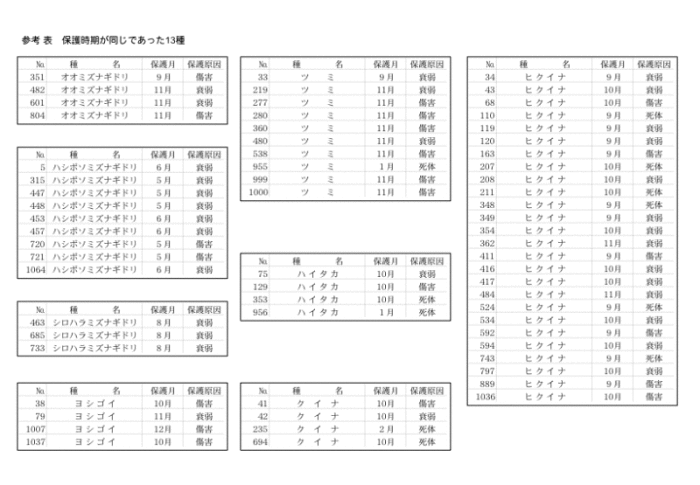
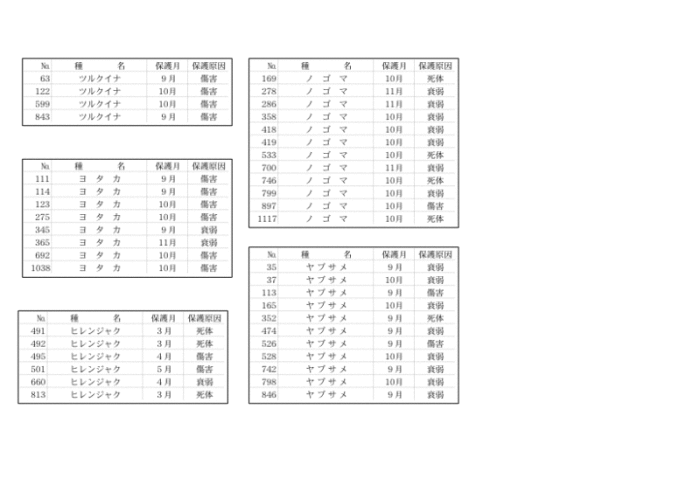
オオミズナギドリは秋、ハシボソミズナギドリは春、シロハラミズナギドリは夏に保護と、それぞれの種が決まった時期に保護されていた。これは、偶然の一致かどうかは確認できないが、このように同一の時期に保護が多い事は、何か共通した原因があると考えられる。また、他の鳥にも保護の時期が同じものが何種かあったので、ミズナギドリ同様に以下の表を見て参考にしてほしい。この表を見ると、大半が秋の渡りに保護されている。それと、図5の月別保護件数でも、秋の渡りに保護件数が極めて多くなっていることがわかる。これは多分その年に生まれた幼鳥が、初めての渡りで衰弱したり、事故にあったりする事が多いからと考えられる。保護記録には成長、幼鳥等のこまかい分類データはなかったが、記憶では秋期に保護された鳥は確かに幼鳥が多かったように思う。また、ヒレンジャクは保護した時期が、春の渡りの頃だけであった。当地方ではヒレンジャクは、春の渡り以外に観察例が少ない事から、春と秋では渡りのコースが違うことが考えられる。
今回のデータ整理でもうひとつ注目したのは放鳥率であった。日頃の保護活動をするなかで、常に「放鳥率は死亡率より高く。」と云う目標値があった。集計では放鳥率が死亡率より2.9%高くこの目標は達成されていた。また保護原因別の放鳥率・死亡率は、ひなの放鳥率が非常に低かった。これは、ひなを育てることがいかに難しいかを実証するものであった。
(注意:現在、日高高校生物部では傷病鳥獣の保護活動は行っていません。)
御坊市 教育委員会 教育課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5525 ファックス:0738-24-0528
お問い合わせフォーム


















更新日:2023年06月15日